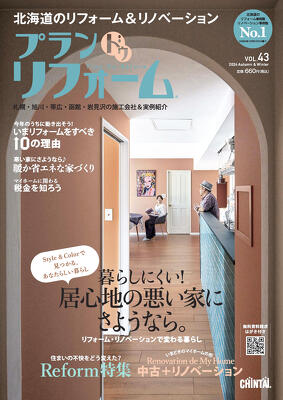2世帯暮らし
親の本音、子の気持ち。二世帯同居の成功の秘訣!
若夫婦どちらの親と同居するのか。同居するのは両親か、片親か。若夫婦に子どもは何人いるか。リフォームするのは夫婦宅かそれとも親の家か――
ちょっと数えてみたただけでも二世帯同居のリフォーム計画を左右する要素は、どれも軽視できないものばかり。新しい住まいで快適に、そして仲良く暮らしていくために、リフォーム計画の際に考慮すべきいくつかのポイントを子の視点と親の視点両方からとりあげてみました。

■食事と生活リズム
水回り、共有か分離か
●子の気持ち――娘
同居するのは父母と娘のわたしなので〈我が家の味〉は親世帯も子世帯も同じようなもの、だからキッチンも一緒でいいと思っていました。けれども、いざ二世帯住宅のプランをつくる段になると、ちょっと考え直しましたね。
やっぱり、若い人と年配者では、食事の傾向がかなり違うんです。とくに子どもがいると、食卓に肉料理やカレー、ピザなどが並ぶことが多いし、育ち盛りだから量もたっぷり。たびたび親をつきあわせるわけにはいかないですよね。だから世帯ごとに別々のキッチンを設けることにしました。
でも、魚料理や鍋物、そば、うどんなどは母と一緒につくって、二世帯が一緒に食卓を囲むことにしています。煮物も母のがおいしいし(笑)。
●親の気持ち――母
わたしたちの場合、親世帯と子世帯の生活リズムにかなり差がありましてね。晩ご飯の時間帯がずれることが多いんです。だったら交代で使うのに都合がいいから、キッチンは一階にひとつでいいだろうと思ってました。
でも親世帯の食事のしたくや後片付けが済んだかと思うとすぐに子世帯のが始まることになるでしょ。きっと落ち着かないだろうと思って、キッチンは、すっきりと別々にしたんです。
あとは、お風呂は共有ですが、トイレは別々。まだ夫婦ともに健康ですけれども、将来のことを考えてバリアフリーの広いトイレにしました。
共有するか分離するか、それぞれの世帯の生活リズムを考えて検討しました。キッチンもトイレも共有のほうが工事費は抑えられたのでしょうが、毎日のことですから、親世帯と子世帯がどちらも我慢せず、気兼ねなく自由に使えるようなリフォームにして、よかったと思います。
■家事分担とプライバシー
いい関係をつくるには
●子の気持ち――嫁
かなり分かって慣れてきたつもりですけれど、「掃除」の感覚、やっぱり義母とは違うんですよね。わたしは、まとめて一気に片付けるタイプなので、こまめに掃除する義母がリビングのホコリをつまんで捨てるのを見たりすると、ちょっと申し訳ない感じになったりして。
うちはリビングやキッチンを共有した二世帯リフォームにしましたが、共有スペースの掃除や管理は、どちらがどうするか、はっきり決めないままにしておいたんです。気がついた人がやればいいと。わたしはパート勤務をしているので、結局、家に長くいる義母の役目になることが多くて。
その分、お風呂掃除やレンジの手入れで挽回しようと思っているんですよ。これも、いままでのところ旦那にやってもらうことが多いのですが(苦笑)。
●親の気持ち――姑
ええ、もう掃除機をかけ出したら、みんな一緒です。居間から廊下、玄関、階段と、全部やってしまいます。嫁も最初は気がとがめるような様子でしたが、きれい好きは、わたしの性分でね。それに掃除はけっこうな運動になって、いいんですよ。わざわざウォーキングなんかする必要がないくらい。
もう小学校高学年ですから、孫にも手伝ってもらっています。いろいろ指示して掃除のしかたを教えるのが、自然としつけにもなってるんでしょうね。
家に汚れたところ、散らかったところがあると気になってしょうがないのですが、息子夫婦の部屋と子ども部屋には手をつけません。そこはプライバシーの尊重です。
■孫の教育どこまで
子世帯を補助する気持ちで
●子の気持ち――嫁
「おじいさん、おばあさんが孫を甘やかして」という声をよく耳にしますが、夫の父はできた方なので、子どもの教育、しつけについては心配ないどころか、かえって頼もしいと感じています。
リフォームして二世帯同居にしたのは、それも理由の一つなんです。女の子と男の子、ふたりの子どもがまだ小さいので、二世帯リフォームに際しては子ども部屋を個室にしていません。自分の育った環境を考えたら、寝るところは別にしても、勉強部屋は中学生くらいまで一緒でもいいような気がしています。
せっかくの二世帯同居なので、子どもが大きくなっても、自室に閉じこもらずに、祖父といろいろと話をしやすいような間取りを考えたつもりです。
●親の気持ち――舅
今回リフォームして同居することになった息子にも、子どもの頃のように接するわけにもいかないでしょうね。もう長く離れて暮らしていたのですから、生活の感覚が変わっています。
食習慣や子どものしつけなどは、それぞれの家庭の文化ですから、急に改めさせたり、こちらの言い分を押し付けるわけにはいきません。違いがあって当たり前。親世帯と子世帯が一緒に暮らしていく中で、折り合いをつけていくことになるのでしょうね。
息子のお嫁さんには、孫のしつけなども期待されていますけれども、教育は子世帯が責任を持つのが本来のあり方でしょうから、過干渉にならないようにしようと思っています。
■介護への備えを忘れず
自宅で長く過ごすためのバリアフリー
●子の気持ち――息子
母はまだまだ達者ですけれども、やはり高齢者。必要ないとは言うのですが、介護の可能性は当然、視野に入れてのリフォームです。大きなけがをすると年寄りは身体の衰えが進みやすいと聞いていたので、家庭内事故を防ぐ意味でも同居を機会にバリアフリーにしました。
十数年前に父を病気で亡くしました。それまで病院とは無縁の人でしたから、できる限り在宅療養をして、慣れ親しんだ自宅で過ごせたのは、よかったと思います。あの時、バリアフリーにしておけたら、本人も世話をする家族も、もっと安心感をもち、負担を少なくして暮らせたかもしれない。そんな思いもあってのリフォームでした。
●親の気持ち――母
子どもたちが独立してからはずっと2 階の部屋は布団部屋と衣装部屋になっていたので、リフォームを機会に思い切って整理。息子夫婦に住んでもらった方が有効活用できますしね。
ただ、長年暮らして愛着のある住まいですから、あまり大きな改変をしないようにしてもらいました。わたしの日常生活は、これまで通り、だいたい一階だけで済むようにしています。
いまはまだ布団に寝ていますけれども、身体が衰えるとベッドの方が寝起きが楽なそうですから、将来はベッドも入れられるように寝室をリフォームしてもらいました。
■リフォーム資金と相続
遠慮しない、後でモメない
●子の気持ち――息子
そろそろ持家かな、というタイミングで、わたしの両親との二世帯同居にしました。親のほうからの希望が大きかったものですから。
両親宅を二世帯用にリフォームすることになったのですが、費用のほとんどは親がもつことに。
なんだか負い目を感じてしまって、新しくなる住まいについても要望を述べるのが遠慮がちになりますね。わたしよりも妻のほうが、もっとそう感じているのでは。家の名義とか相続(兄弟3人)とか、親がしっかりしているうちに、先々のことも決めておかないとならないでしょうね。
●親の気持ち――父
ええ、息子と嫁さんに面倒を見てもらうことになるだろうから、せめてリフォーム資金くらいは出そうと思ってね。前々からそのつもりで貯めていたものです。
ふつうに考えたら、この後、わたしらよりも息子夫婦のほうがこの家に長く住むことになります。だから、お前たちの使いやすいように決めなさいとは言っているんですがね。まだちょっと遠慮をしているみたいですね。
この家、便利な立地で、いい環境なので、離れがたくてね。また息子たちがいずれ自分の子と二世帯同居でもしてくれたら、なんて思っています。
■同居世帯の関係性
だれも窮屈な思いをしないように
●子の気持ち――娘
夫はわたしの親との同居には抵抗はなかったみたい。実の母娘だから、ぼくが嫁と姑の板ばさみになる心配がないって。むしろ自分の親との同居よりもいいと言っています。
わたしたちの家に父母の部屋を増やすかたちでリフォームしたのですが、リビングでくつろいでもらえるよう思い切って広くしました。自然に団らんが生まれるような工夫です。
親子ということで生活感覚が同じなので、キッチンは共有でだいじょうぶ。いつも楽しくおしゃべりしながらご飯支度をしています。
●親の気持ち――母
二世帯とは言っても娘との同居なので、よくありがちな気苦労は無しで済んでいます。そういうこともあって、なんとなく家の中ではわたしたちの発言権が大きくなっちゃってね。物事をいろいろと仕切っちゃうことも多くて。
娘のだんなさんが、またおとなしい人なの。
ないがしろにしてるわけではないけれども、夫の立場というものを大事にしてあげなくちゃと反省することもあるんです。会社の同僚や取引先の方なども気兼ねなくお招きできるような雰囲気にはしておかないとね。
リフォームをして客間に使えるスペースを設けておいたのは、そんなことを考えていたからでもあるんです。